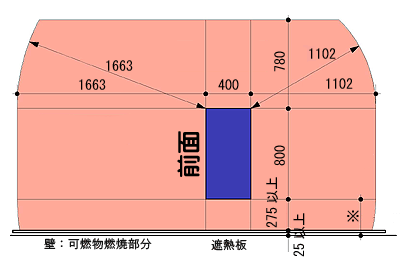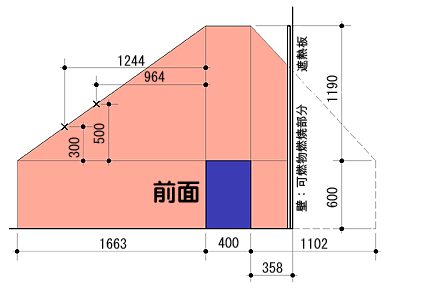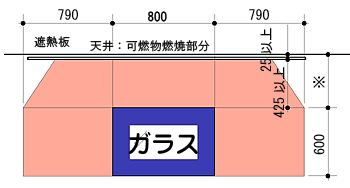���z��@�@����
����21�N2��27���@��225��
| ���s�R�ޗ��ł��������̎d�グ�ɏ�����d�グ���߂錏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���̍����́A�Z��A���O�n�E�X�A�ʑ��ȂǂɃX�g�[�u�Ȃǂ�ݒu����ۂɎ����S�Ă����s�R�ނŎd�グ��K�v���������]���̌��z��@�̈������ɘa���鍐���ł���B�������A���̍����̈����͏Z��Ɍ��肳��Ă���B����ēX�܂◷�قȂǂɗp���邱�Ƃ��o���Ȃ��B�i���p�Z��œX�ܕ���1/2��������50��2�����Ȃ�ΓK�p�\�j |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����ƂȂ�C�͂S��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��ꍆ�@�@�R�����i�d�M��R�����j ��@�@�X�g�[�u ��O���@�@�Ǖt�g�F ��l���@�@����� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���@��2���@�X�g�[�u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | �������e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �X�g�[�u���̑�����ɗނ�����́i��щɂ��Ђ�h�~����\�����̑��̖h�Ώ�x��̂Ȃ��\���ł����āA1�b�ԓ�����̔��M�ʂ�18kw�ȉ��̂��̂Ɍ���B�ȉ����̍��ɂ����āu�X�g�[�u���v�Ƃ����B�j��݂�����
���̃C���̓��Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ����A���ꂼ�ꓖ�Y�C���̓��ɒ�߂�ޗ��̑g�����ł��邱�ƁB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ŋ߂͒g�F�Ȃǂ��C���e���A���g�[�@�Ƃ��Đ݂���ꍇ�����邪�A�C�g�p���Ƃ��Ă̋K�肵���Ȃ������̂őS�ď��s�R�ȏ�ŕ����K�v���������B���̋K��ɂ��g�F��u���������R�������̖ؒ���������\�ł���B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �C | �X�g�[�u���̐������e�͈� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �X�g�[�u���̐������e�O�����̊e�_�i���Y�������e�O���������_��L����ꍇ�ɂ����ẮA���Y���_�������B�j�ɂ�����@���ɐ����ȕ��ʂł����ē��Y�e�_����̍ŒZ���������̕\�Ɍf���鎮�ɂ���Čv�Z�����X�g�[�u���R���R�Đ��������ł���_���܂ނ��̂ň͂܂ꂽ�����̂����A���Y�X�g�[�u���̕\�ʂ̊e�_�ɂ��āA���Y�e�_�𐂒�����Ɏ���(1)�̋K��ɂ��v�Z�����X�g�[�u���R���R�Đ������������ړ������Ƃ��ɂł���O�Տ�̊e�_�i�ȉ����̍��ɂ����ĒP�Ɂu�O�Տ�̊e�_�v�Ƃ����B�j���A���������Ɏ���(2)�̋K��ɂ��v�Z�����X�g�[�u���R���R�Ċ���������ړ������Ƃ��ɂł���O�Ղ͈͓̔��̕����i��艏�A���䂻�̑������ɗނ��镔�����܂ޏꍇ�ɂ����ẮA���Y�����̎d�グ�����s�R�ޗ��ł������̂Ɍ���B�ȉ����̍��ɂ����āu�X�g�[�u���R���R�ĕ����v�Ƃ����B�j�̊Ԓ��y�щ��n�����s�R�ޗ��Ƃ����ꍇ�i���̏ꍇ�������B�j
����(3)�y��(4)�Ɍf����ޗ��̑g�����ł��邱�ƁB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | �@ �ՔM��݂����ꍇ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����(1)����(3)�܂łɒ�߂���@�ɂ��A�X�g�[�u���R���R�ĕ����̕Njy�ѓV��̎����ɖʂ��镔���ɑ���ΔM�̉e�����L���ɎՒf����Ă���ꍇ
�Njy�ѓV��̎����ɖʂ��镔���̎d�グ���R�ޗ����ł��邱�ƁB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �n | ����s�R�ޗ��͈̔� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �C���̓��̋K��ɂ�����炸�A�����̉��M���̒��S�_�𐅕�������25�����ړ������Ƃ��ɂł���O�Տ�̊e�_���A���������80cm�ړ������Ƃ��ɂł���O�Ղ͈͓̔��̕����̕Njy�ѓV��̎����ɖʂ��镔���̎d�グ�����s�R�ޗ��ł�����̂Ƃ���B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �j | �͂�ꂽ�͈͂̊O�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �C���̓��ɋK�肷�镔���ȊO�̕����̕Njy�ѓV��̎����ɖʂ��镔���̎d�グ���R�ޗ����͕���12�N���ݏȍ�����1439����1��2���ɋK�肷��؍ޓ��i�ȉ��u��R�ޗ����v�Ƃ����B�j�ł�����̂Ƃ���B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����12�N���ݏȍ�����1439���́A ���@ 1���@�V������s�R�ޗ��ł��邱�� 2���@�ǂ͖؍ށA���A�\���p�p�l���A�p�[�e�B�N���{�[�h�Ⴕ���͑@�۔Ŗ��͖؍ޓ��y�ѓ�R�ޗ��ł��邱�ƁB ��� 1���@�؍ޓ��̕\�ʂɁA�Ή��`��������������悤�ȍa��݂��Ȃ����ƁB 2���@�؍ޓ��̎�t���@�����̂Ƃ���ɂ��� �@�C�@10mm�ȏ�̏ꍇ�A�ǂ̓����ʼnΉ��`����h�~����悤�Ɏ�t���A���͓�R�ޗ��̕ǂɒ��ڎ��t����B �@���@�؍ޓ���100mm�ȉ��̏ꍇ�́A��R�ޗ��̕ǂɒ��ڎ��t����B �ǂ�����A�؍ތ���25mm����ꍇ��OK�ł��B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �g�b�v�y�[�W�F���z��@�ɂ��� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ADS-�RD�f�[�^�̃_�E�����[�h�ƌ��z���TOP�� Free Collection of 3D Material-�����RD�f�ނƔw�i���e�N�X�`�����@ �y�؎{�H�Ǘ��Z�m�̎��͐f�f-�������ɒ���� ���z�{�H�Ǘ��Z�m�̎��͐f�f-�������ɒ���� �ǍH���{�H�Ǘ��Z�m�̎��͐f�f-�������ɒ���� �����{�H�Ǘ��Z�m�̎��͐f�f-�������ɒ���� ���z�m�̎��͐f�f-�������ɒ���� ���z�ݔ��m�̎��͐f�f-�������ɒ���� �����Z���R�[�f�B�l�[�^�[�̎��͐f�f-�������ɒ���� ���h�ݔ��m�E�댯���戵�҂̎��͐f�f-�������ɒ���� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||