解答と解説:
解答と解説:
解答と解説:
解答と解説:
解答と解説:
解答と解説:
解答と解説:
解答と解説:
ただし、反力が上向きの場合「+」、下向きの場合「-」とする。
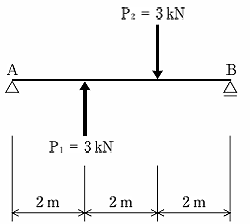
| 1 | -3kN | ||
| 2 | -1kN | ||
| 3 | +1kN | ||
| 4 | +3kN |
解答と解説:
ただし、曲げモーメントは材の引張側に描くものとする。
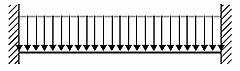
| 1 | 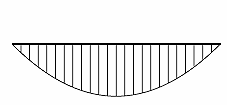 |
2 | 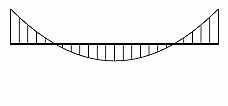 |
| 3 | 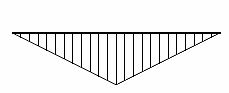 |
4 | 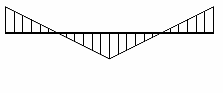 |
解答と解説:
解答と解説:
解答と解説:
解答と解説:
解答と解説:
平成20年度 2級建築施工管理技術検定試験
| 受検種別受検種別ごとに解答する問題No.と選択による解答数の内訳 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| No1〜No14までの 14問題のうちから 9問題を選択し、解答してください。 |
| 解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
| No1 | 伝熱に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | 熱伝導抵抗は、材料の厚さが同じ場合、グラスウールの方がコンクリートより大きい。 | |||||||||||||||||
| 2 | 壁面の熱伝達率は、壁の表面に当たる風速が大きいほど小さい値となる。 | |||||||||||||||||
| 3 | 壁体は、熱貫流率が大きいものほど断熱性能が低い。 | |||||||||||||||||
| 4 | 建物の室内温度は、熱容量の大きい建物ほど外気温の変動に対して緩やかに変化する。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No2 | 採光及び照明に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | 光天井照明は、室内の照度分布が均等になり、照明による影がやわらかくなる。 | |||||||||||||||||
| 2 | 均斉度は、室内の照度分布の均一性を表す指標で、最高照度に対する最低照度の比で示される。 | |||||||||||||||||
| 3 | 演色性は、物の色の見え方に影響を与える光源の性質をいう。 | |||||||||||||||||
| 4 | 人工光源は、色温度が高くなるほど赤みがかった光色となる。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No3 | 色の心理的効果に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | 色の温度感覚には、暖色や寒色と、それらに属さない中性色がある。 | |||||||||||||||||
| 2 | 壁の上部を明度の低い色、下部を明度の高い色で塗り分けると、安定感が生じる。 | |||||||||||||||||
| 3 | 色の派手、地味の感覚は、一般に、彩度が高いほど派手に感じられる。 | |||||||||||||||||
| 4 | 実際の位置よりも遠くに見える色を後退色、近くに見える色を進出色という。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No4 | 構造計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | 構造体は、その変形により建築非構造部材や建築設備の機能に支障をきたさないように設計する。 | |||||||||||||||||
| 2 | 耐震計画上、建物の平面形状は、複雑な形をできるだけ避ける方がよい。 | |||||||||||||||||
| 3 | 建物に耐震上設けるエキスパンションジョイント部のあき寸法の検討には、建物の高さを考慮する必要はない。 | |||||||||||||||||
| 4 | 建物の上下階において、剛性、耐力、重量の急変はできるだけ避ける。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No5 | 木造在来軸組構法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | 真壁は、壁の仕上げ面を柱と柱の間に納め、柱が外面に現れる壁をいう。 | |||||||||||||||||
| 2 | 土台は、柱の下部に配置して、柱からの荷重を基礎に伝えるために用いられる。 | |||||||||||||||||
| 3 | 火打梁は、桁と梁の交差部に入れ、骨組の水平面を堅固にするために用いられる。 | |||||||||||||||||
| 4 | 胴差は、垂木を直接受けて屋根荷重を柱に伝えるために用いられる。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No6 | 鉄筋コンクリート構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | 梁の断面算定にあたっては、コンクリートの引張強度は無視する。 | |||||||||||||||||
| 2 | 鉄筋の許容付着応力度は、コンクリートの設計基準強度に関係なく一定とする。 | |||||||||||||||||
| 3 | あばら筋は、梁のせん断補強に用いられる。 | |||||||||||||||||
| 4 | 構造耐力上主要な梁は、全スパンにわたり複筋梁とする。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No7 | 鉄筋コンクリート構造と比較した鉄骨構造の建築物の一般的な特徴に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | 同じ容積の建築物では、構造体の軽量化が図れる。 | |||||||||||||||||
| 2 | 構造部材の設計にあたっては、座屈についての検討が重要である。 | |||||||||||||||||
| 3 | 鉄骨は、腐食しにくく、かつ、熱の影響を受けにくい。 | |||||||||||||||||
| 4 | 大スパンの建築物が可能である。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No8 | 構造設計における荷重及び外力に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | 床の積載荷重の値は、床の構造計算をする場合と大梁の構造計算をする場合で異なる数値を用いることができる。 | |||||||||||||||||
| 2 | 風力係数は、建築物の断面及び平面の形状に応じて定められている。 | |||||||||||||||||
| 3 | 地震層せん断力係数は、上階になるほど小さくなる。 | |||||||||||||||||
| 4 | 雪止めが無い屋根の積雪荷重は、屋根勾配が60 度を超える場合には0とすることができる。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No9 | 図に示す集中荷重を受ける単純梁の支点Bにおける反力の値として、正しいものはどれか。 ただし、反力が上向きの場合「+」、下向きの場合「-」とする。 |
|||||||||||||||||
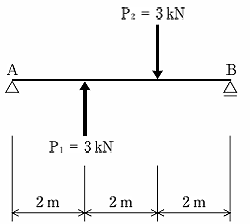 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No10 | 図に示す等分布荷重を受ける両端固定梁の曲げモーメント図として、正しいものはどれか。 ただし、曲げモーメントは材の引張側に描くものとする。 |
|||||||||||||||||
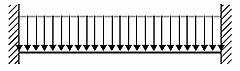 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No11 | 普通ポルトランドセメントと比較した各種セメントの一般的な特性に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | フライアッシュセメントB種を用いたコンクリートは、長期強度が小さい。 | |||||||||||||||||
| 2 | 早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートは、低温でも強度発現が早い。 | |||||||||||||||||
| 3 | 中庸熱ポルトランドセメントを用いたコンクリートは、水和熱が小さく、乾燥収縮も小さい。 | |||||||||||||||||
| 4 | 高炉セメントB種を用いたコンクリートは、化学的な作用に対する抵抗力が大きい。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No12 | 木材に関する一般的な記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | 木材の辺材部分は、心材部分より含水率が高い。 | |||||||||||||||||
| 2 | 気乾状態とは、木材の水分が完全に無くなった状態をいう。 | |||||||||||||||||
| 3 | 木材の熱伝導率は、含水率が小さいほど小さくなる。 | |||||||||||||||||
| 4 | 木材の強度は、繊維飽和点以上では、含水率が変化してもほぼ一定である。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No13 | 石材の一般的な性質に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | 大理石は、耐酸性が優れている。 | |||||||||||||||||
| 2 | 安山岩は、耐火性が優れている。 | |||||||||||||||||
| 3 | 凝灰岩は、耐久性が乏しい。 | |||||||||||||||||
| 4 | 花こう岩は、耐火性が乏しい。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| No14 | 木製建具に関する一般的な記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
| 1 | かまち戸は、4辺をかまちで組み、鏡板をはめ込んだものである。 | |||||||||||||||||
| 2 | 格子戸は、日除けと通風を目的として、縦がまちの間に羽板を取り付けたものである。 | |||||||||||||||||
| 3 | ふすまは、骨組の両面にふすま紙を張り、4周に縁をはめ込んだものである。 | |||||||||||||||||
| 4 | 障子は、周囲にかまちを回し、縦横に細かい組子を設け、これに障子紙を張ったものである。 | |||||||||||||||||
|
解答と解説: |
||||||||||||||||||
| TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||