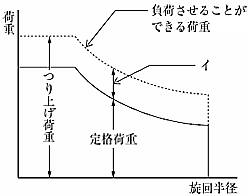| No36 |
仮設工事に関する用語とその説明の組合せとして、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
墨出し |
------ |
工事に必要な寸法の基準となる位置や高さなどを、所定の場所に表示する作業 |
| 2 |
やり方 |
------ |
建築物の高低、位置、方向、通り心の基準を明示する仮設物 |
| 3 |
縄張り |
------ |
工事の着工に先立ち、隣地や道路との境界測量を行い、縄などで敷地境界を表示する作業 |
| 4 |
心出し |
------ |
各部位の中心線を出して心墨を表示する作業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No37 |
地盤調査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
平板載荷試験は、地盤のN値を調べる試験である。 |
| 2 |
ハンドオーガーボーリングは、小規模な建築物の地盤調査に使用される。 |
| 3 |
サンプリングとは、地盤の土質試料を採取することをいう。 |
| 4 |
粒度試験により土の粒度組成を数量化し、砂質土と粘性土に分類することができる。 |
|
解答と解説:
答え--- 1
平板載荷試験は、地盤反力を求め、地盤の許容支持力を求める。
|
|
| No38 |
埋戻しに関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
埋戻し部分にあるラス型枠材は、撤去の必要はない。 |
| 2 |
透水性のよい山砂を用いる場合は、締固めは水締めとする。 |
| 3 |
透水性の悪い山砂を用いる場合は、厚さ30 cm程度ごとにローラー、ランマーなどで締め固める。 |
| 4 |
山留め壁と地下躯体との間の深い根切りの埋戻しは、砂質土と粘性土を交互に組み合わせて締め固める。 |
|
解答と解説:
答え--- 4
埋戻しには、粘性土を用いることは一般的に無い。
|
|
| No39 |
山留め工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
ソイルセメント柱列山留め壁工法は、鋼矢板工法に比べ、壁の剛性を高くできる。 |
| 2 |
場所打ち鉄筋コンクリート山留め壁工法は、軟弱地盤や深い掘削に適している。 |
| 3 |
アイランド工法は、水平切梁工法に比べ、切梁の長さを短くできる。 |
| 4 |
親杭横矢板工法は、法付けオープンカット工法に比べ、掘削土量や埋戻し土量が多い。 |
|
解答と解説:
答え--- 4
オープンカット工法は総掘りのため、掘削土量や埋戻し土量が多い。矢板の方が圧倒的に土量は少なくてすむ。
|
|
| No40 |
地業工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
砂地業に用いる砂は、締固めが困難にならないように、シルトなどの泥分が多量に混入した砂を避ける。 |
| 2 |
砂利地業に用いる砂利は、砂混じりの切込砂利よりも粒径のそろった砂利を用いるのがよい。 |
| 3 |
砂利地業では、締固め後の地業の表面が所定の高さになるよう、あらかじめ沈下量を見込んでおく。 |
| 4 |
捨てコンクリート地業は、掘削底面の安定化や、基礎スラブ、基礎梁のコンクリートの流出あるいは脱水を防ぐために粗雑にならないように施工する。 |
|
解答と解説:
答え--- 2
砂利地業は、大小の砂利混じりのほうが良く締まる。
|
|
|
|
| No41 |
鉄筋の加工又は組立てに関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
スラブ筋の結束は、鉄筋相互の交点の半数以上とした。 |
| 2 |
鉄筋の曲げ加工は、常温で行った。 |
| 3 |
鉄筋の切断は、電動カッターによって行った。 |
| 4 |
柱や梁の鉄筋の組立ては、点付け溶接で行った。 |
|
解答と解説:
答え--- 4
鉄筋の組立ては強度に影響するので原則的に溶接は行わない。
|
|
| No42 |
鉄筋の継手又は定着に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
梁筋の定着長さは、柱の打増し(ふかし)を行う場合は打増し部分を除いて算定する。 |
| 2 |
柱のスパイラル筋の末端部には、フックを設ける。 |
| 3 |
梁筋の重ね継手の長さは、一般に下端筋より上端筋の方を長くする。 |
| 4 |
D25 の異形鉄筋は、重ね継手としてもよい。 |
|
|
解答と解説:
答え--- 3
小梁の場合なら上端が40dの場合でも、下端は25dになる。全ての梁ではない。
|
|
| No43 |
型枠工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
相対する型枠の間隔を一定に保持するために、セパレーターを用いた。 |
| 2 |
梁の側型枠の寸法を梁下端までとしたので、底型枠を梁幅の寸法で裁断した。 |
| 3 |
壁の窓開口部下部の型枠に、コンクリート打設時の点検用の開口を設けた。 |
| 4 |
コンクリート躯体図に基づき型枠加工図を作成し、型枠パネルの加工を行った。 |
|
解答と解説:
答え--- 2
底型枠は梁側壁を受けて組むのが一般的である。レベル調整、盛替えなどの施工性でも逆は好ましくない。
|
|
| No44 |
コンクリートの調合に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
|
|
| 1 |
コンクリートに含まれる塩化物量(塩化物イオン換算)は、原則として0.30 kg/m3 以下とする。 |
| 2 |
細骨材率が大きすぎると、流動性の悪いコンクリートとなる。 |
| 3 |
細骨材の粗粒率が大きい場合には、細骨材率を小さくする。 |
| 4 |
単位セメント量の最小値は、コンクリートの種類によって異なる。 |
|
解答と解説:
答え--- 3
細骨材の粗粒率が大きい場合、細骨材率は大きくする。
|
|
| No45 |
コンクリートの養生に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
コンクリート打込み後の散水養生は、一般に水分が不足してくる7日目以降に始めるのがよい。 |
| 2 |
コンクリートの硬化初期には、強い風などの気象作用からコンクリートの露出面を保護しなければならない。 |
| 3 |
コンクリートの硬化初期に振動が加わると、強度の発現が損なわれる。 |
| 4 |
コンクリートの養生期間中の温度が低いと、強度の発現が遅延する。 |
|
解答と解説:
答え--- 1
7日目では既に硬化がほとんど完了しているので効果が少ない。2〜3日目位に実施する。
|
|
|
| No46 |
鉄骨の工作に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
ケガキ寸法は、製作中に生じる収縮、変形及び仕上げ代を考慮した値とする。 |
| 2 |
ショットブラスト処理は、摩擦接合における摩擦面の処理として認められていない。 |
| 3 |
板厚13 mm を超える鋼板の切断は、せん断切断としてはならない。 |
| 4 |
ポンチ、タガネによるケガキは、曲げ加工される部分の外面に行ってはならない。 |
|
解答と解説:
答え--- 2
摩擦面の処理にはショットブラスト処理を用いる。
|
|
| No47 |
高力ボルト接合に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
セットを構成する座金及びナットには表裏があるので、逆使いしないようにした。 |
| 2 |
高力ボルトと溶接の併用継手は、高力ボルトを先に締め付け、その後溶接を行った。 |
| 3 |
接合部組立て時に積層した板間に生じた2mm以下のボルト孔の食違いを、リーマー掛けで修正した。 |
| 4 |
建方時に用いた仮ボルトを、本締めに用いるボルトとして使用した。 |
|
解答と解説:
答え--- 4
使用した仮ボルトは本締め時には交換する。
|
|
| No48 |
鉄骨製作工場における錆止め塗装に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
素地調整で鋼材表面に粗さを与えると、塗膜の付着性が向上する。 |
| 2 |
工事現場溶接を行う部材は、開先面以外はすべて塗装を行う。 |
| 3 |
ブラスト法による錆落しを行った場合には、ショッププライマーなどを塗装しなければならない。 |
| 4 |
塗膜に膨れや割れが生じた場合には、その部分の塗膜をはがしてから再塗装する。 |
|
|
解答と解説:
答え--- 2
コンクリート巻き込みをする部分なども塗装をしない。
|
|
| No49 |
図に示すジブクレーンの性能曲線において、イに該当する荷重として、最も適当なものはどれか。 |
|
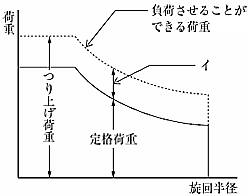 |
| 1 |
カウンターウェイトの重量に相当する荷重 |
| 2 |
つり具の重量に相当する荷重 |
| 3 |
ブームの重量に相当する荷重 |
| 4 |
風荷重に相当する荷重 |
|
解答と解説:
答え--- 2
定格荷重から負荷させることができる荷重までの間は、吊具部分の荷重が相当する。
|
|
| No50 |
ALCパネル工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
床パネルに、電気配管用の溝掘りを行った。 |
| 2 |
外壁パネルの取付けは、表裏を確認して行った。 |
| 3 |
パネルの取付け金物には、防錆処理を行った。 |
| 4 |
横壁ボルト止め構法のパネルの受け鋼材は、積上げ段数5段ごとに設けた。 |
|
解答と解説:
答え--- 1
水平パネルに溝堀は強度が劣るので実施してはならない。
|
|
|
|
|