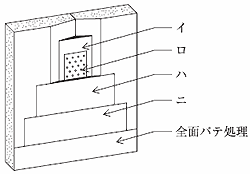| No51 |
アスファルト防水工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
保護コンクリート仕上げの場合に用いる絶縁用シートの重ね幅は、100 mm とした。 |
| 2 |
出隅及び入隅の増張りのストレッチルーフィングの幅は、300 mm とした。 |
| 3 |
アスファルトルーフィングの重ね幅は、長手、幅方向とも100 mm とした。 |
| 4 |
平場のルーフィングと立上りのルーフィングの重ね幅は、100 mm とした。 |
|
|
|
|
|
| No52 |
外壁の張り石工事において、湿式工法と比較した乾式工法の特徴として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
地震時の躯体の挙動に追従しにくい。 |
| 2 |
台車等の衝突で張り石が破損しやすい。 |
| 3 |
白華現象、凍結による被害を受けにくい。 |
| 4 |
石裏と躯体とのあき寸法が大きい。 |
|
解答と解説:
答え--- 1
乾式工法の方が金具等を利用するので躯体の挙動に追従しやすい。
|
|
| No53 |
金属製折板葺の工法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
けらば包みの継手部は、重ね内部にシーリング材を挟み込んで留めた。 |
| 2 |
重ね形折板の重ね部に使用する緊結ボルトの流れ方向の間隔は、600 mm とした。 |
| 3 |
軒先には、折板の先端部分の下底に尾垂れを付けた。 |
| 4 |
水上部分の壁との取合い部に取り付ける雨押えの立上げは、50 mm とした。 |
|
解答と解説:
答え--- 4
雨押えの立上げは、150mm以上立ち上げる。
|
|
| No54 |
住宅屋根用化粧スレート葺(平形屋根用スレート)に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
下葺には、アスファルトルーフィング940 に適合するものを使用した。 |
| 2 |
葺足は働き長さ以下とし、水切り重ね長さを確保した。 |
| 3 |
葺き方は、水下の軒先から水上の棟に向かって順に葺いた。 |
| 4 |
軒板は、本体の屋根スレート施工後に、専用釘で留め付けた。 |
|
解答と解説:
答え--- 4
住宅屋根用化粧スレート葺は軒先から施工する。
|
|
| No55 |
軽量鉄骨壁下地に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
スタッドの高さに高低差があったので、高い方に適用される部材の種類を使用した。 |
| 2 |
出入口開口部の垂直方向の補強材は、鋼製天井下地の野縁材に固定した。 |
| 3 |
コンクリート壁に添え付くスタッドは、打込みピンで壁に固定した。 |
| 4 |
スタッドには、床ランナーの下端から1,200 mm 間隔で振れ止めを設けた。 |
|
解答と解説:
答え--- 2
出入口開口部の垂直方向の補強材は、床から上部スラブ又は梁まで達するようにし、溶接又はボルトで取り付ける。野縁材に固定では不可。
|
|
|
|
| No56 |
金属工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
アルミニウム製笠木は、コーナー部材より直線部材を先に取り付けた。 |
| 2 |
アルミニウム製笠木をはめ込むための固定金具は、パラペットにあと施工アンカーで固定した。 |
| 3 |
バルコニーに設置するアルミニウム製の手すり笠木の端部は、外壁のコンクリートに埋め込まないようにした。 |
| 4 |
丸鋼タラップは、型枠に先付けし、コンクリート打込みとした。 |
|
解答と解説:
答え--- 1
アルミニウム製笠木コーナー部を先行して取付け、直線部分でカットして調整する。
|
|
| No57 |
コンクリート面の仕上塗材仕上げにおける下地調整に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
屋外や室内の湿潤になる場所の下地調整に用いるパテは、合成樹脂エマルションパテを使用した。 |
| 2 |
仕上塗材の付着性の確保や目違いの調整のため、セメント系下地調整塗材を使用した。 |
| 3 |
外装厚塗材C(セメントスタッコ)仕上げなので、セメント系下地調整塗材を使用した。 |
| 4 |
複層塗材E(アクリルタイル)仕上げなので、合成樹脂エマルション系下地調整塗材を使用した。 |
|
|
解答と解説:
答え--- 1
合成樹脂エマルションパテは水性である。耐水性、耐湿性、耐アルカリ性等を求められる部位には向かない。湿気の多い部分は塩化ビニル樹脂系パテなど水に強いものがよい。
|
|
| No58 |
せっこうプラスター塗りに関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
調合で砂を多く入れると、強度が増す。 |
| 2 |
下塗りは、下地モルタルが十分乾燥した後施工する。 |
| 3 |
上塗りは、中塗りがあまり乾燥しないうちに施工する。 |
| 4 |
塗り面の凝結が十分進行した後、適度の通風を与える。 |
|
|
解答と解説:
答え--- 1
砂を多く入れると強度は低くなる。そのかわり収縮が少ないのでクラックが生じにくい。
|
|
| No59 |
アルミニウム製建具に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
建具枠の取付けは、くさびで仮止めし、建具枠のアンカーを躯体付けアンカーに溶接した。 |
| 2 |
モルタルに接する箇所に、耐酸塗料を塗布した。 |
| 3 |
建具隅部の小ねじ留めの位置は、水が溜まりやすい部分を避けた。 |
| 4 |
建具枠周囲の充填に、容積比でセメント1:砂3の調合モルタルを用いた。 |
|
解答と解説:
答え--- 2
モルタルはアルカリなので耐アルカリ性の塗料を採用する。
|
|
| No60 |
塗装工事における木部の素地ごしらえに関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
付着したアスファルトや油類は、皮すきで取り除き、溶剤でふいて乾燥させた。 |
| 2 |
透明塗料塗りの素地面で、仕上げに支障のおそれがある甚だしい変色は、漂白剤を用いて修正した。 |
| 3 |
杉や松などの赤みのうち、やにが出ると思われる部分には、との粉を塗布した。 |
| 4 |
素地の割れ目や打ちきずなどは、ポリエステル樹脂パテで埋めて平らにした。 |
|
解答と解説:
答え--- 3
との粉では、ヤニは止まらない。ヤニ止め効果のあるシーラーを下地に塗布する。
|
|
|
| No61 |
塗装の種類と素地の組合せとして、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
アクリル樹脂エナメル塗り |
---- |
モルタル面 |
| 2 |
ウレタン樹脂ワニス塗り |
---- |
木部面 |
| 3 |
合成樹脂調合ペイント塗り |
---- |
モルタル面 |
| 4 |
フタル酸樹脂エナメル塗り |
---- |
木部面 |
|
|
|
|
解答と解説:
答え--- 3
合成樹脂調合ペイントはアルカリに弱いのでモルタル面には向かない。
|
|
| No62 |
内装木工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
敷居、鴨居の溝じゃくりは、木裏側に行った。 |
| 2 |
幅木の出隅は、見付け留めとした。 |
| 3 |
木製三方枠の戸当りは、付樋端(つけひばた)とした。 |
| 4 |
サッシの額縁には、ボードを差し込むための壁じゃくりを付けた。 |
|
解答と解説:
答え--- 1
木材は木表に向って反る傾向があるので、溝じゃくりは、木表側に行う。
|
|
| No63 |
合成樹脂塗り床に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
施工法には、流しのべ工法、樹脂モルタル工法、コーティング工法及びライニング工法がある。 |
| 2 |
コンクリートの表層のぜい弱な部分は、あらかじめ研磨機などで除去する。 |
| 3 |
立上り部は、だれを生じないように粘度を調節したペーストを用いる。 |
| 4 |
防滑のための骨材の散布は、前工程の塗膜が硬化した後に、むらのないように均一に散布する。 |
|
解答と解説:
答え--- 4
防滑のための骨材の散布は塗膜が硬化前に行う。
|
|
| No64 |
図に示すテーパー付せっこうボードの継目処理工法のイ〜ニの工程として、最も不適当なものはどれか。 |
|
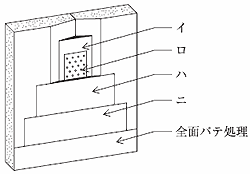 |
| 1 |
イ |
---- |
ジョイントコンパウンド下塗り |
| 2 |
ロ |
---- |
ジョイントテープ張り |
| 3 |
ハ |
---- |
寒冷紗張り |
| 4 |
ニ |
---- |
ジョイントコンパウンド上塗り(サンドペーパー掛け) |
|
|
|
|
|
|
解答と解説:
答え--- 3
ハ、はジョイントコンパウンド下塗りである。寒冷紗張り・繊維ジョイントテープは、ベベル目地、突付目地などのときに用いる。
|
|
| No65 |
カーテン及びブラインド工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 |
| 1 |
ベネシャンブラインドの手動の操作形式は、ギヤ式、コード式及び操作棒式に分類される。 |
| 2 |
ケースメントカーテンは、厚地であり、遮光、遮へい、保温、吸音などの目的で用いられる。 |
| 3 |
遮光用(暗幕用)カーテンの下端は、窓の下枠より400 〜500 mm程度長く仕上げる。 |
| 4 |
カーテンボックスの幅は、窓幅に対して、一般に片側各々100 〜150 mm程度伸ばす。 |
|
解答と解説:
答え--- 2
ケースメントカーテンは、遮光性カーテンと薄手カーテンの中間に当たるカーテンである。厚地、遮光の目的のカーテンはドレープカーテンと呼ぶ。
|
|
|
|
|